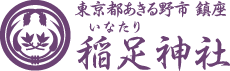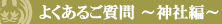参拝や人生儀礼、当神社に関してよく尋ねられる質問をまとめました。
Q: 稲足神社の御祭神はどんな神様ですか?
A: 古事記では淤母陀琉神(おもだるのかみ)と阿夜訶志古泥神(あやかしこねのかみ)、日本書紀では面足尊(おもだるのみこと)と惶根尊(かしこねのみこと)と表される男女二柱の神様です。
天地の活動が始まった時、神世七代と呼ばれる神々が現れました。七代のうち最初の二代は性別を持たない独神であり、三代め以降は男女二柱で一代を成す神々でした。この神世七代の六代めが面足尊と惶根尊です。ちなみに七代めが国生みで有名な伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)です。面足尊と惶根尊がどのような神様であったのかについては諸説あります。面足尊は「面が足る」ことから容貌や身体が充実すること、「面」を大地と捉え、後の国生みに繋がる準備が整った様子を表すと言われています。惶根尊は「阿夜訶志古泥神(あやかしこね)」が感動詞「あや」、恐れ多いの意を示す形容詞語幹「かしこ」で構成されていることから、感動する様子、意識の発生を表すと言われています。また、結婚して国を生む伊弉諾尊、伊弉冉尊の一代前ということから、結婚直前の見目麗しく活力に満ちた男女の神々として、心身ともに整った健康・美容のご利益があると言われています。
日本では長く神道と仏教とが融合する神仏習合の時代が続いてきたため、面足尊と惶根尊も神世七代の六代めということから仏教における第六天魔王(他化自在天)と結び付けられました。第六天、大六天の呼び名でも広く信奉されています。「ご由緒・ご祭神」のページもあわせてご参照ください。
天地の活動が始まった時、神世七代と呼ばれる神々が現れました。七代のうち最初の二代は性別を持たない独神であり、三代め以降は男女二柱で一代を成す神々でした。この神世七代の六代めが面足尊と惶根尊です。ちなみに七代めが国生みで有名な伊弉諾尊(いざなぎのみこと)、伊弉冉尊(いざなみのみこと)です。面足尊と惶根尊がどのような神様であったのかについては諸説あります。面足尊は「面が足る」ことから容貌や身体が充実すること、「面」を大地と捉え、後の国生みに繋がる準備が整った様子を表すと言われています。惶根尊は「阿夜訶志古泥神(あやかしこね)」が感動詞「あや」、恐れ多いの意を示す形容詞語幹「かしこ」で構成されていることから、感動する様子、意識の発生を表すと言われています。また、結婚して国を生む伊弉諾尊、伊弉冉尊の一代前ということから、結婚直前の見目麗しく活力に満ちた男女の神々として、心身ともに整った健康・美容のご利益があると言われています。
日本では長く神道と仏教とが融合する神仏習合の時代が続いてきたため、面足尊と惶根尊も神世七代の六代めということから仏教における第六天魔王(他化自在天)と結び付けられました。第六天、大六天の呼び名でも広く信奉されています。「ご由緒・ご祭神」のページもあわせてご参照ください。
Q: 神棚をお祀りする際に気を付けることはありますか?
A: 神棚や御神札が南か東を向くようにしてお祀りします。目線よりも高い位置にてお祀りしますが、扉や出入口の上など頻繁に人の出入りがある場所の上にはお祀りしないようにしてください。
Q: 神棚に御神札をお納めする時はどうすればよいでしょうか?
A: 最近よく見かけるものですと一社造りと三社造りの神棚が一般的ですが、それぞれでお祀りの仕方が若干異なります。一社造りの神棚の場合手前から天照皇大神宮(神宮大麻)、氏神神社、崇敬神社の御神札の順に重ねてお納めします。三社造りの場合は真ん中に天照皇大神宮、向かって右に氏神神社、向かって左に崇敬神社の御神札をお納めします。
Q: 昇殿祈願(ご祈祷)の際の服装はどのようなものがよいでしょうか?
A: 神様の前に出るのに相応しい服装でおいでください。カジュアルな服装であっても襟付きのものをお勧めします。社殿内では靴を脱ぐため、靴下や足袋などをご着用ください。また本殿まで50段ほど階段を上るので、履きなれた靴をご用意されることをお勧めいたします。
Q: 昇殿祈願(ご祈祷)にかかる時間はどのくらいですか?
A: ご参列される人数にもよりますが、祭祀の時間は30~40分ほどです。